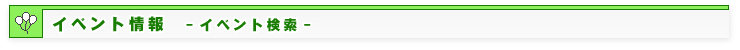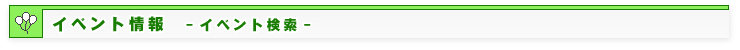所蔵品展5 日展−つながる画家たち− 所蔵品展5 日展−つながる画家たち−
多くの画家は、師弟であったり仲間や親子といった、様々な繋がりの中からいろいろな影響を受け、画風を確立させていきます。このたびは日展の日本画家という括りで紹介していきます。
日展は、明治40(1907)年、フランスのサロンに倣って文部省が主催となって開いた展覧会(文展)が始まりで、以降「帝展」「新文展」「日展」と名称をかえて今日まで続く総合美術展です。第1章・第1室では、文展の審査員でもあった竹内栖鳳を中心に、栖鳳の画塾・竹杖会で学んだ橋本関雪、上村松園らの作品と共に、栖鳳が顧問を務めた国画創作協会の画家たちを展示し、第2室では栖鳳の孫弟子にあたる山口華楊が代表を務めた晨鳥社の画家たちなど、京都画壇で学んだ画家同士の繋がりを紹介します。
第2章では、民営化した日展をけん引した東山魁夷、杉山寧、高山辰雄の3人が東京画壇の中心となった様子を紹介します。親子、孫、家族といった繋がりをもつ東山魁夷と川崎家一門との関係や、魁夷の弟子たちの作品のほか、杉山寧、高山辰雄と日展の気鋭作家らが結社した一采社と、一采社のメンバーと交流のあった画家など幅広く紹介します。 |